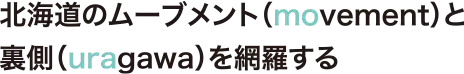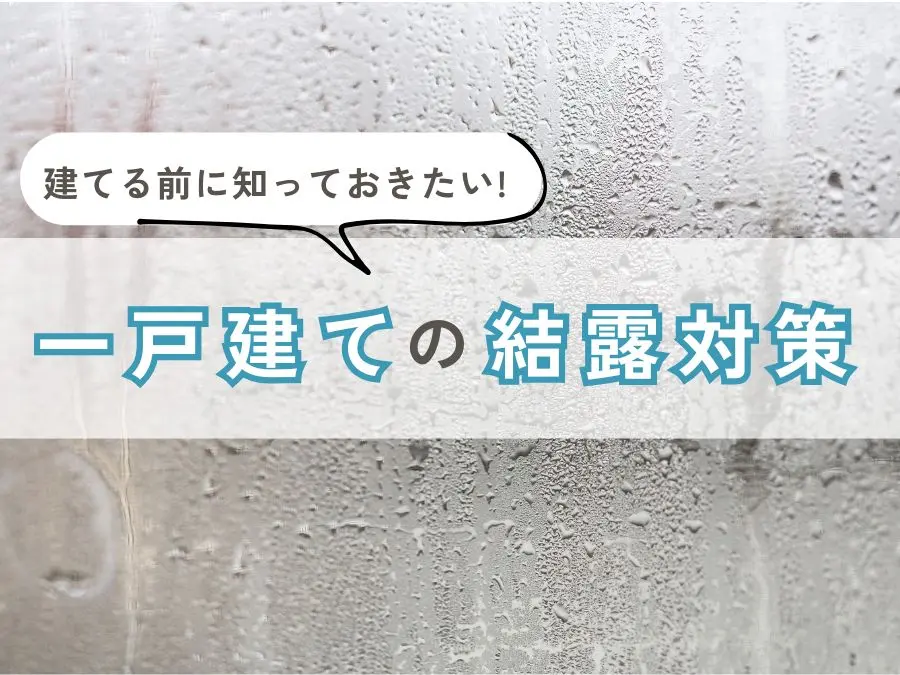
提供:北海道マイホームセンター
建てる前に知っておきたい!一軒家の結露対策
「アパートの結露がすごいから、家を建てるときは絶対結露しないようにしたい!」
「せっかく家を建てるのに、湿気で家がカビたらイヤだ」
「カビのアレルギーがあるから、家の湿気対策はしっかりやりたい」
北海道の冬は外と家のなかとの寒暖差が大きく、湿気や結露に対してこんな不安を持っている方もいるのではないでしょうか。
そこでこちらの記事では、結露が起こりにくい家づくりから、結露を防ぐ暮らし方までを徹底解説します!
結露に不安な気持ちを抱いている方は、ぜひ最後までご覧ください。
結露が起こりにくい家づくりのポイント
結露を防ぐには、家の中に湿気をため込まないことが重要です。
こちらでは、湿気をためない家づくりのために知っておきたい、暖房、断熱材、換気システムの選び方を解説します。
【暖房】水蒸気が発生しにくいものを選ぶ
結露を予防するには、水蒸気が発生しにくい暖房である、パネルヒーターや床暖房を選ぶのがおすすめです。
アパートやマンションなどで広く使われている灯油ストーブやガスストーブは、灯油やガスを燃焼させる際に水蒸気を発生させます。
パネルヒーターや床暖房は、ボイラーで温めた不凍液や温風を利用しておうち全体を温めるため、水蒸気が発生せず結露の心配が少なくなります。
現在、北海道の住宅でよく採用されているセントラルヒーティングは、パネルヒーターや床暖房を利用して家の中を均一に暖かくする暖房です。
▼セントラルヒーティングの種類と特徴
| セントラルヒーティングの種類 | 特徴 |
| 温水式 | ボイラーで不凍液を温め、各部屋のパネルヒーターに循環させて家を温める暖房システム。
風を起こさないのでホコリが舞いにくく、乾燥しにくい。 |
| 温風式 | ボイラーで作った温風を、各部屋に送風して家を温めるシステム。 温水に比べて冷めやすいため、規模の小さい建物に向いている。 |
温水式のセントラルヒーティングは結露の予防や空気の乾燥対策のほか、熱損失が少ないというメリットもあるため、多くの住宅や施設で採用されています。
【断熱材】水に強い種類を選ぶ
結露と聞くと窓についた水滴を思い浮かべるかもしれませんが、実は壁の中でも結露が発生する可能性があります。
そこで重要なのが、断熱材の選び方です。
結露を防ぐためには、水に強い断熱材を選ぶ必要があります。
▼断熱材の種類と特徴の例
| 断熱材の種類 | 特徴 |
| ウレタンフォーム | 湿気が入りにくく、遮音性も良いが、耐火性は弱い。 |
| グラスウール | ローコストで害虫被害が少ない。水には弱いため、湿気対策には工夫が必要。 |
| ポリスチレンフォーム | 耐水性が高く、断熱性にも優れる。耐火性は弱い。 |
湿気や断熱性を重視するなら、ウレタンフォームを壁や床のなかに吹き付ける工法がおすすめ。
他の断熱材に比べてコストはやや高くなる傾向にありますが、隙間をしっかりと埋めるため、断熱性や防音性に優れ、長期間劣化しにくいことがメリットです。
【換気システム】第一種または第三種を選ぶ
24時間換気システムは3種類ありますが、住宅では第一種換気または第三種換気を選ぶのが一般的です。
それぞれの換気システムのおおまかな違いは、外の空気を家の中に取り込む「給気」と、家の中の空気を外へ送り出す「排気」の仕組みにあります。
▼換気システムの種類と特徴
| 換気システムの種類 | 特徴 |
| 第一種換気 | 給気と排気の両方を機械で行なうため、安定的に空気の入れ替えができる。部屋の温度を一定に保ちやすい。 |
| 第二種換気 | 給気のみを機械で行なう。排気は取り込んだ空気が自然に室内の空気を押し出す形で行なわれる。 |
| 第三種換気 | 排気のみを機械で行なう。結露が起こりにくく、電気代も安い。 |
第二種換気は排気が自然的に行われるため湿気が室内に残りやすく、第一種や第三種換気に比べて結露が起こりやすくなります。そのため、一般的に住宅で採用されるのは第一種または第三種の換気システムとなります。
第一種は外気の影響を受けにくいため、寒い日でも部屋を暖かく保ちやすいのがメリットです。一方、給気も排気も機械的に行うため、電気代が高くなりやすい特徴があります。
第三種は排気のみ機械で行なうため、第一種に比べて電気代は安くなる傾向にあります。結露が起こりにくくコストが安いのが魅力な一方で、室温が外気の影響を受けやすいため、冷え込む日には部屋が暖まりにくいと感じることがあるでしょう。
換気システムはハウスメーカーによっても差があるため、どんな換気システムを使っているのかよく確認したいですね。
結露を防ぐ暮らし方のポイント
結露を防ぐには、暮らし方にもちょっとしたコツがあります。
以下では3つの結露を防ぐポイントを解説します。
【室温】部屋同士の温度差に注意する
部屋同士に温度差があると、結露が発生する可能性があるため、なるべく温度差がでないようにしましょう。
たとえば、リビングに家族が集まっている場合で考えてみます。
全室を温めるセントラルヒーティングを使うのがもったいないから、電気ストーブやオイルヒーターでリビングだけを温める、ということをしていると、暖房を使っていない部屋では結露が起こりやすくなってしまいます。
空気は暖かいほうから冷たいほうへ移動する性質があります。
それと同じように、湿度も高いほうから低い方へ移動します。
人が集まって汗や料理などから発生した水蒸気が、暖かい部屋から冷たい部屋へ移動するとどうなるでしょうか?
冷たい空気は、暖かい空気に比べて水分を含むことができません。そのため、温められていない部屋で結露が起こりやすくなってしまうのです。
結露を防ぐには、部屋同士の温度差が大きくならないよう、注意してくださいね。
【換気システム】正しく使う
結露を防ぐには、換気システムを正しく使うことも重要です。
フィルターや換気口は換気性能が落ちないよう、3カ月に1回程度は掃除したいところ。
フィルターはお手入れしていても経年劣化してしまうため、年に1回を目安に新しいものに取り換えることも大切です。
「換気システムを使うと寒く感じる」と、スイッチを切りたくなったり、換気口を閉じたくなったりすることもあるかもしれません。しかし、換気口を閉じたりスイッチを切ったりしてしまうと、家の中に湿気を含んだ空気がとどまってしまいます。
寒さを感じるときは、換気システムの風量を調整すれば室温が外気の影響を受けづらくすることが可能です。結露を防ぐために、換気システムは止めないようにしてください。
とくに建ててから3年以内の新築住宅は、基礎のコンクリートや木材、クロスに水分が含まれるため、換気システムは常に運転させておいてくださいね。
【窓ガラス】断熱シートを貼る
新築で家を建てる場合、複層ガラスに樹脂製のサッシを組み合わせた、断熱性の高い窓が採用されているため、結露の心配は非常に少なくなっています。
しかし、洗濯物を窓際にたくさん干していたり、加湿器を使っていたりすると結露が起きてしまうことも。
そんなときは、窓に断熱シートや吸水テープを貼ることで結露対策ができます。
ホームセンターや100均で手軽に購入できるので、費用も安く、すぐに取り組める対策方法です。
ただし、断熱シートや吸水テープが濡れているのを放置するとカビの発生に繋がる恐れがあります。
断熱シートや吸水テープが濡れていたら、拭き取るか取り替えて、しっかりお手入れしてくださいね。
快適な家づくりを目指して
以上、おうちの湿気対策についてご紹介しました。
北海道の住宅は機密性が高く、24時間換気システムをきちんと使っていれば、結露することは非常に少なくなっています。
しかし、洗濯物を干していたり、人が集まっていたりすると、窓に水滴がついてしまうことも。
今回紹介したポイントを押さえて、対策してみてくださいね。
北海道マイホームセンターには、さまざまなハウスメーカーのモデルハウスが集まっています。
結露はもちろん、それ以外のお悩みもお気軽にご相談ください!