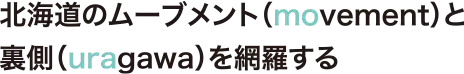提供:札幌市
【開催レポート】「未来の札幌を知る!よくわかるGXセミナー~GX・AI基本編~」を開催しました
札幌市は今年度、Team Sapporo-Hokkaidoの協力のもと、主に高校・大学生から30歳代の若年層を対象に「GX・金融」に関する理解促進を図るためのセミナーの開催を2回予定しています。
その1回目が「未来の札幌を知る!よくわかるGXセミナー~GX・AI基本編~」と題して、10月11日(土)、札幌市北区にある北海道大学 Sky HALLを会場に、250人の参加者、オンライン配信で100人以上がリアルタイムで視聴する中、開催されました。
セミナーは、人気教育系YouTuber「ヨビノリたくみ」氏がスペシャルゲストとして登場。3部構成で各セッションの専門家・有識者が登壇し「GX・AI・金融」の基礎を学びながら、これからの北海道・札幌の可能性を考えていくという内容でした。
ヨビノリ氏の軽快なトークとクイズもまじえた進行は「わかりやすかった」「聞きやすかった」という多くの参加者からの声も聞こえ、北海道・札幌のより良い暮らしへの示唆に富んだセミナーとなりました。
※この記事では、セミナー内容を抜粋した開催レポートをお届けします!
セミナーの開催概要はこちらをご参照ください。
■セッション1「GXとは?」
スピーカー:石井 一英 氏(北海道大学 大学院工学研究院 環境工学部門 教授)
石井:GXっていうと、グリーントランスフォーメーション。Gはグリーンだっていうことになります。経産省がつくった言葉なんですけど、化石燃料をできるだけ使わず、グリーンなエネルギーを活用していくための変革や、その実現に向けた活動のことをいいます。最近百年で気温が2.1℃上昇しています。このままだと21世紀末には4.8℃ぐらい気温が上がってしまいます。
ヨビノリ:もう4.8℃だと大変なことだと思います。
石井:札幌市のシンボル的なお祭りである雪まつりですら危なくなってきてますし、豪雨は4.6倍になるということで、非常に問題視されています。
ヨビノリ:そうですか、雪まつり行ったことないので早く行かないと。
石井:札幌市では、2050年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするゼロカーボンを目指しています。石炭、石油、LNGといった化石燃料を使う生活からたくさん二酸化炭素が出てきます。化石燃料が温室効果ガスの結構な原因となっているんですね。それをどんどん減らさなければいけない。森林の木は二酸化炭素を吸収しながら大きくなっていきます。その能力と人間の活動によって出てしまう二酸化炭素の排出量を釣り合うようにプラスマイナスゼロになるまで減らしましょうというのがゼロカーボンなんです。これが、なかなか難しいんですね。エネルギーは、熱と燃料、電気の三つのカテゴリーに分かれるんですが、今、世界中では電気を使っている30%ぐらいは再生可能エネルギーです。熱のうちまだ10%、燃料のうちまだ3.5%しか再生可能エネルギーになっていないんです。GXの社会に本当にしようと思ったら、太陽光、風力も当然大事なんですけど、この熱と燃料の部分をなんとかしなければいけません。
ヨビノリ:全くなってないですね。電気の方だけクリアしてるんですね。
石井:寒い北海道は特に灯油を使う。また、とても広いので市町村の移動にかかる燃料をなんとかしないと北海道にGXの未来はないということになってしまいます。
ヨビノリ:なるほど。これを使わないようにする社会にしていこうというのがGXですよっていうことなんですね。
石井:皆さんの家庭から出る二酸化炭素の排出量を見るとですね、半分ぐらいが電気。1/4ぐらいが自動車、もう1/4が灯油とガスから出ています。
GXを進めるためには省エネ、再エネを導入するだとか、あるいは移動する時に、できるだけ公共交通を使うだとか、ごみの分別、北海道産の木を使うだとかが大事です。ダイエットをするかのように省エネをしていくということなんですね。
ヨビノリ:習慣を変えていかなきゃいけないよという話ですか。
石井:それくらいコツコツやらなければいけないよということなんですね。お知らせしたいのは、かなりの部分が皆さんのコツコツ運動が効きますということです。
それから、北海道は今、皆さんが使っている電気の37%が再エネです。世界では30%、日本全体だと22%ぐらいですので、北海道はやっぱり再エネはかなり進んでいるんだなと思います。
じゃあGXで何が変わるんだということですけど、公害が社会的に深刻な問題だった時は経済が優先であったため、経済優先すると環境が汚れる。それから環境を優先すると、少し工場とかに設備投資が必要となるので、経済がちょっと落ちるというふうトレードオフに関係だったんですね。GXというのは、環境も良くするし、経済も良くする経済と環境をウィンウィンにしようというのが本質的な話なのです。
ヨビノリ:確かに、今まで相反するもののイメージでした。
石井:そう、今まで相反するものが同じベクトルだということになります。皆さんに知ってほしいのは、北海道のポテンシャルということで、太陽光、風力、中小水力、地熱発電、バイオマス、全国北海道は何位でしょうか。ヨビノリさんどうでしょう。
ヨビノリ:気持ちよく全部一位かなとも思ったんですが、一つだけ一位じゃないと思うものがあります。地熱発電って温泉とかないとかいけないから、一位は大分県かな。
石井:そう、地熱だけ二位なんですよ。今問題になっているように、再生可能エネルギーって地域との共生、自然との共生がやっぱり重要になっていて、こういうものを無視して、再エネ、再エネって言われると、ちょっと問題があると思っています。今日最後の問題になりますけれども、経済的なことを考えるとですね、日本っていうのは海外にものすごくエネルギーのお金を払っています。再エネで30%ぐらいある北海道ですら、まだお金払ってます。
ヨビノリ:厳しいですね。
石井:厳しいです。
日本がエネルギーの輸入に支払っている代金はだいたい16兆円から24兆円になります。これの1割でも2割でも払わずに済んでですね、各地域にお金が落ちれば、相当な財源になると思います。こういった財源にしようというのが、再生可能エネルギーということで、GXは地産地消の考え方でやっていこうということなのです。
江戸時代前は、奈良とか京都とかに文化経済の中心がありました。東京、江戸から現在までは石油時代です。GXになったら東北越えて北海道が中心になると思うんですよ。食べ物も美味しい、エネルギーもある。こんないいところ、パラダイスはないかなと。それからもちろん皆さんの働く場所もこれからできてくるということです。
ヨビノリ:中心地が変わるかもしれないってことですね。
石井:将来のまちづくりを頂点にしながら、自然を大切にして地域の課題を乗り越えて、みんなで登っていきましょう。GXはあくまで手段です。皆さんの幸せな生活を皆さんで築いていきましょうっていうのが私からのメッセージです。
■セッション2「GX産業の未来」
スピーカー:田中 真子 氏(エア・ウォーター グリーンイノベーション開発センター センター長)
田中:今日は企業がGXに向けてどんな活動をしているのかっていうのを、ヨビノリさんとお話をしていきたいと思います。
私は大阪のエア・ウォーターという会社で働いてるんですが、なぜ北海道で今、お話をさせていただいているのかというと、GX、カーボンニュートラルのポテンシャルが北海道はとっても大きいということで、いろいろな活動をしています。
ヨビノリさんは意外に思うかもしれませんが、実はエア・ウォーターが始まったところはこの北海道札幌の地。なので、北海道の皆さんにとても親しみのある会社なんですね。
田中:エア・ウォーターという会社は何の会社かっていうと、ガスの会社です。一般的にどんなガスを作ってるかっていうと、地球上に存在している空気を分離して、酸素とか窒素とかアルゴンそして、炭酸ガスとか水素、ヘリウムといったものも作っています。いわゆる産業ガスを作っている会社なんです。
ヨビノリ:産業ガスっていう単語は、そもそもあまり身近じゃないですよね。
田中:ちょっと一般的には知られてないと思うんですけど。最近は水素で動くクルマが走っていたりしますね。こういうところに産業ガスを供給しているような会社になります。産業ガスの水素は宇宙で一番多く、最も軽い元素で、燃やしても二酸化炭素を出さない、とても地球に優しいエネルギーとして取り扱われるんですが、ちょっと危ない、爆発の危険性があるガスともいえます。
ヨビノリ:たしかにそういったイメージはありますね。
田中:これを認識して、安全に取り扱うと危険ではないガスですが、これからもっともっと広がっていけばいいなと思っています。水素が今、どんなところに使われているかというと、FCV、燃料電池はどんどん広がっています。昨年は札幌の大通に、大きな水素ステーションをオープンしました。
ヨビノリ:そうなんですか。まだ見たことないです。水素ステーション自体もしかしたら見たことないかもしれません。
田中:ぜひ、一度みてみてください。水素はなかなか需要拡大していくのが難しく、最初は自家用車から供給していこうかと思っていたんですけど、やはり広がらないということで、バス、トラックとか、要は商用車であれば物流に欠かせないということで、商用車向けの水素ステーションとして大通にオープンしました。ぜひ一度見てみてください。
ヨビノリ:なるほど、普通のステーションとは違うわけですね。
田中:水素の勉強はここまでで、次からですね。札幌以外の地域でやっている取り組みについて、三つご紹介したいと思います。
一つ目は鹿追町。鹿追町では、牛のふん尿を原料にしてバイオガスをつくっています。バイオガスの成分であるメタンを水素にして、町で走る燃料電池車とか、チョウザメの飼育施設のエネルギーとして使用しています。国内で唯一、家畜のふん尿から水素を作って商用化している取り組みです。
二つ目は豊富町です。豊富町は世界でも珍しい、油温泉という温泉が湧いているんです。この温泉とともに出てくるガスをクリーンなエネルギーとして取り出せたらいいよねという考えから、温泉ガスを分解して水素とカーボンをとっています。
ヨビノリ:なんかこれ、化学を勉強し始めた子どもが適当にやっちゃう夢の化学反応みたいなやつですか。悪いもの一個もないですよねこれは。
田中:そうなんです。でもできちゃうんですよ。作った水素を豊富町の牛乳を作る工場に供給して、燃料として使ってもらおうと思います。もう一つ言いたいのが、雇用を創出することです。地域の方はもちろんですが、温泉に湯治に来られる方が、ちょっとアルバイトしながら、健康になれる働きってそういうのがいいなと思って取り組んでいます。
ヨビノリ:健康になれる働き口ということなんですね。
田中:三つ目は、帯広市・大樹町でロケットの燃料になるカーボンニュートラルな液化バイオメタンというものを作ろうとしています。取り組みを始めたきっかけは、酪農家さんの声からなんです。田舎だから電線がない、電気以外の用途で牛のふん尿からつくったエネルギーをつくってくれないかと相談されたんですね。
ヨビノリ:電線ないのは盲点ですね。電気ってつくったらいいってことでもないですからね。貯めておくこと、送るものがないとダメという側面がありますよね。
田中:そうなんです。バイオメタンを液としてそのまま使える用途を探そうということで取り組みをはじめました。今、大樹町のロケットの燃料に使えるように一緒に燃焼試験をやらせていただいています。北海道発でこのようなバイオメタンも世界に広げていけたらいいなと思っています。
■セッション3「GXで描く北海道・札幌の未来地図」
パネリスト:石井 一英 氏(北海道大学 大学院工学研究院 環境工学部門 教授)
田中 真子 氏(エア・ウォーターグリーンイノベーション開発センターセンター長)
中村 拓哉 氏(調和技研 代表取締役社長)
鈴木 徹 氏(北海道新聞社 編集局 特別編集委員兼解説委員)
ヨビノリ:トークセッションということで、いろいろな方に来ていただいております。こちらでは、より具体的な話を聞いていければと思います。
中村:私は、AIの研究をしている会社を17年前に立ち上げたんですが、お話を聞いて、自分のやっていることも非常にGXに近いなって感じました。例えば、風力の発電みたいなものをどのタイミングで発電すると一番効率よく回るかとか、宅配の経路をどう通ったら一番最適で燃料の軽減につながっていくかとかAI研究の分野といえます。
ヨビノリ:GXでもAIで問題を解決していくという需要はますます上がりそうですね。続けて、具体的に今回のセミナー内容であるGXと札幌市民の関わりについて教えてほしいんですけど、石井先生お願いできますか。
石井:GXとね個人の関わりということなんですが、2050年にゼロカーボンになる社会を考える時に何が必要かというと行動変容といわれていまして、皆さんが少しずつエネルギーの使い方を変えて、省エネをしていき、毎日の生活の中でできることを少しずつやっていかないと、実質ゼロにはならないということなんです。
ヨビノリ:個人個人が考えて行動して達成できる目標なんですね。個人個人ができる取り組みついて、鈴木さんは何かありませんか。
鈴木:例えば学生のみなさんなら、これから就職する企業や自治体などで、環境負荷や温暖化ガスを減らす取り組みを進めること。あるいは消費者として、そうした取り組みに熱心な企業の商品を優先的に買うことが有効です。実は、そうした企業をきちんと評価し、成長させていく取り組みはすでに始まっています。環境・社会・企業統治の改善に取り組む企業を選んで投資する「ESG投資」という投資手法です。ESG投資の金額はすでに全世界で1兆ドルを超え、逆に環境などを重視しない企業が資金を集められない世の中になりつつあります。その意味で、札幌市はとても先進的です。昨年、国のGX金融・資産運用特区に認定され、ESG投資資金を世界中から集め、道内や全国、アジアに供給する「マネーセンター」を目指しています。このように、みなさんの身近な選択や行動は、企業の行動を、さらには世界のお金の流れまで変えていくのです。
ヨビノリ:買う時の選択でも変えていけれるんだということですね。今日は若い方が会場では多いのですが、締めくくりとしてメッセージがあればお願いします。
石井:今日参加している皆さんは、これから社会人になると社会を変える一員になっていくと思います。どんな職業についても、必ず未来の社会のためには役に立つと思うんです。その中でGXの割合がどんどん大きくなってきます。2050年、2100年にはGXが当たり前の社会になっていくと思いますので、皆さんもGXの分野にどうぞチャレンジしていただきたいなと思います。
田中:せっかくポテンシャルを秘めている札幌、北海道に住まわれているので、地域の課題ってなんだろうと考えて欲しいと思います。具体的な課題をちょっと自分で想像して見ていただけたら嬉しいなと。今日は学生さんいっぱいいらっしゃいますので、問題意識を持つことで、もっともっとカーボンニュートラルの取り組みっていうのが推進できていくと思います。
ヨビノリ:一人ひとりの熱いメッセージを感じました。綺麗事だけではうまくいかないし、みんなで考えていかないとGXは推進しないんだなと実感しました。本日はありがとうございました。