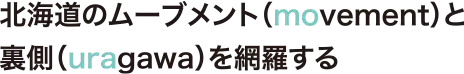【ジンギスカンの発祥】実は軍服の副産物だった?!誕生の経緯を徹底解説!
北海道を代表するグルメといえば、「ジンギスカン!」と答える方が多いのではないでしょうか。
農林水産省の「うちの郷土料理」や北海道遺産にも登録されている料理です。
日本語にはない響きを持つ名前ですが、その発祥は一体どこなのでしょうか?
「そんなことを考えたこともない」というくらいジンギスカンは北海道民にとって当たり前の存在ですが、今回はそのルーツに迫ります!
ジンギスカンの発祥はどこ?名前の由来は?
花見や海水浴など、イベントといえばジンギスカンでパーティーをするのが習慣になるほど、道民にとって身近な料理であるジンギスカン。
その発祥は一体どこなのでしょうか?
こちらでは、ジンギスカンという料理が生まれた経緯や名前の由来を解説します。
ジンギスカンは軍服の「副産物」
ジンギスカンは軍服の副産物として誕生した料理と考えられています。
明治時代、防寒性に優れた羊毛が軍服の素材として使用されていました。
しかし、第一次世界大戦によって輸入するのが難しくなってしまいます。
そこで、国内で羊毛を生産するため、政府は「緬羊百万計画」を実行。25年間で100万頭の羊を生産するという計画でした。
結局、1945年の終戦までに生産できたのは18万頭と計画通りには進まなかったのですが、その後も生産は続けられ、1957年には95万頭まで数が増えました。
この間、羊の増産計画にあわせて、羊肉の活用方法も研究されてきました。
「緬羊百万計画」を打ち出した大久保利通は、羊肉を食用として普及させるよう努めます。
日本人には馴染みのなかった羊肉をどのように料理として仕上げていったのか……。
諸説ありますが、満州に渡った日本人が、モンゴルの羊料理にヒントを得て、現在のジンギスカンの形を作り上げていったと言われています。
ジンギスカンの名前の由来は「チンギス・ハン」
ジンギスカンの名付け親は札幌農学校出身の駒井徳三である、と言われています。
駒井氏は満州国で国務長官を勤めた人物で、娘さんによれば「名前をつけることが好きな人」だったとか。
駒井徳三氏の娘、満州野さんが書いたエッセイ「父とジンギスカン」では
ジンギスカン鍋と名付けたのが私の父自身であったらしい。(中略)
蒙古の武将の名(※チンギス・ハンのこと)をなんとなくつけたのかもしれない。
と触れています。
北海道で最初に提供したお店は札幌の「横綱」
北海道ではじめてジンギスカンを提供したお店は、札幌の狸小路にある「横綱」と言われています。
ジンギスカンといえば、あの独特の香りとタレの味が魅力ですよね。
今でこそ、あの香りがクセになる、という方も多いですが、羊肉を食べはじめた当初は「臭くて食べられない」という声が多かったそうです。
そこで醤油や酒、砂糖に香辛料であるニンニクや唐辛子を組み合わせるなどさまざまなタレのレシピが開発されました。
ジンギスカンのタレの発祥は、月寒の種羊場の場長を勤めた山田喜平氏が作ったもの。
そこから試食や改良が重ねられ、「ジンギスカン」をお店のメニューとして提供しはじめたのが、かつて狸小路にあった「横綱」だったのです。
煮込みや豚…派生ジンギスカンのルーツは?
ジンギスカンといえば、生の羊肉を焼いてタレをつけるスタイル、またはあらかじめタレに漬けていた肉を焼いて食べるイメージがありませんか?
実は一部の地域では少し変わった食べ方をしていたり、羊肉ではない新しいジンギスカンが開発されたりしています。こちらでは、派生ジンギスカンの発祥に迫ります。
煮込みジンギスカン
全国テレビに取り上げられて一躍有名になった、名寄市の「煮込みジンギスカン」。
味付きジンギスカンのタレと肉を一緒に深い鍋に入れて、焼きながら煮て食べるのが特徴です。
名寄市の智恵文地区でも、「緬羊百万計画」をきっかけに羊の生産が始まり、羊肉を食べる習慣が広まったそう。
ただ、たっぷりのタレと一緒に焼く独特のスタイルはいつ頃できたものなのか、はっきりとわかる資料は残っていません。
地元の精肉店によれば、「昭和23年には、タレと肉を袋に詰めて量り売りしていた」とのことです。
地元のスーパーでは漬け込みのタレがたっぷり入ったジンギスカンが売られています。
名寄の精肉店では「ジンギスカン2キロください。肉1.5キロ、タレ500グラムで」とタレの量を指定して買うことも可能です。
まだ食べたことがない方は、ぜひご賞味あれ!
豚ジスカン
ジンギスカンのタレに豚肉を漬けたのが「豚(とん)ジスカン」です。
元祖は留萌にある老舗スーパー、「中央スーパー」で、現在は道内の各スーパーでも見かけるようになりました。
羊肉は臭みがあって苦手、という方も食べやすいため、小さなお子さんやクセのある食材が得意でない人も一緒に食べられるのが嬉しいですね。
北海道は「豚肉消費量ランキング」で1位を獲得したこともあるほど、豚肉の消費量が多い地域。
新たなグルメである豚ギスカンも、発祥の地である留萌を中心として多くの道民に親しまれています。
【まとめ】ジンギスカンはまだまだ発展中!
ジンギスカンが誕生したのは、羊毛不足がきっかけだったなんて驚きですね。今では、国産より輸入される量の方が多い羊肉ですが、国内での生産が減っても食文化は定着し、郷土料理にまで成長しました。
豚を使った「豚ジスカン」や、焼くのではなく揚げる「ジンギスカンの唐揚げ」など、アレンジ料理も誕生しています。
ジンギスカンの食文化は、これからも発展し続けてくれそうです。