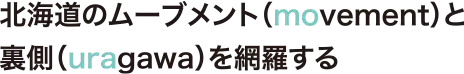長距離ドライブに備えよう!乗り物酔いの仕組みと対策
北海道旅行では車や電車、観光バスなどに長時間揺られることが多く、乗り物酔いに悩まされる人もいることでしょう。この記事では旅の長距離移動をもっと快適にするために、乗り物酔いの仕組みや簡単にできる対策をご紹介します。
なぜ酔うの?乗り物酔いのメカニズム
バランス感覚を司る内耳(三半規管)や視覚、筋肉などの各部位は、それぞれが受け取った刺激などの情報を脳に送信しています。その情報をもとに、脳は「今どのように体が動いているか」を把握しているのです。
しかし、乗り物に乗っているときは、目で見ている景色の動きと内耳で感じている揺れの情報がずれたり、脳内の情報量(刺激量)が過剰になったりして、前庭小脳という部分が混乱してしまうことがあります。
その結果、延髄にある嘔吐中枢や大脳辺縁系が刺激され、不快感や吐き気を引き起こします。また、視床下部が自律神経を調整し、消化器や循環器の働きが乱れ、多様な症状が現れます。これが乗り物酔いのメカニズムです。
ストレスや臭いなども乗り物酔いの原因になる
揺れによる刺激だけではなく、ガソリンなどの臭いによる不快感や、不適切な温度・湿度、精神的な不安・ストレスも乗り物酔いの一因となります。乗り物酔いは様々な要因が複合的に引き起こすものであるため、あらゆる角度から備えておくことが肝要です。
酔う人、酔わない人がいるのはなぜ?
乗り物で酔うか酔わないかは、その人の体質や体調によって左右されるものです。日頃から揺れなどの刺激に慣れている人は酔いにくく、耐性がない人は酔いやすい傾向にあります。
また、睡眠不足や疲労が蓄積された状態だと、通常より軽度な刺激で酔ってしまうこともあるでしょう。幼い頃(4~12歳頃)は情報を受け取る前庭小脳が弱いため、成人よりも酔いやすいと言われています。
乗り物酔いの原因まとめ
- 内耳からの刺激…体のバランス感覚を司る内耳(三半規管・耳石器)が、激しい揺れやスピードによって強い刺激を受ける。
- 視覚情報…ゲームや読書、あるいは車窓から見える景色の動きと、体の揺れにずれが生じる。
- 筋肉・関節からの情報…激しい揺れや振動によって強い刺激を受ける。
- 嗅覚情報…ガソリンや人の臭いによる不快感が酔いを助長する。
- 精神的ストレス…不安やストレスを抱えた状態だと、自律神経が乱れやすく酔いやすい。
車やバス、電車でも!乗り物で酔わないための対策
「乗り物に酔ってしまって、その後の観光が全く楽しめなかった…」という事態もありえます。「自分は酔いやすい体質だな…」とお悩みの方は、旅を満喫するために以下の対策を実践してみてください。
乗り物に乗る前にできること
出発当日、乗車前にできる対策をまとめました。
乗り物・揺れに慣れる
車やバスに乗る訓練をしたり、寝るときに寝返りを打ったりなど、バランス感覚を鍛えることで体を揺れに慣らすことができます。
十分な睡眠をとる
乗り物酔いは疲れや寝不足で悪化しやすいため、前日は十分な睡眠をとることが大切です。出発の数日前から規則正しい睡眠習慣を心がけるとよりよいでしょう。
当日はリラックスできる服装にする
体を締めつける服装は胃腸を圧迫して吐き気を誘発する可能性があるため、できるだけゆったりとした服装を選びましょう。
当日は消化によい食事を適度にとる
空腹および満腹状態は自律神経の乱れにつながるため、消化に良いものを軽く食べておいた方がよいです。
酔い止め薬を適切に服用する
酔い止め薬は乗車の約30分前に飲むのが効果的です。年齢によって服用量が異なるため、説明をよく読んで使用しましょう。
脳の嘔吐中枢を刺激する「ヒスタミン」に対抗し、「抗ヒスタミン薬」をベースにしているものや、自律神経の興奮を緩和したり嘔吐中枢への刺激を遮断したりするタイプも販売されています。「酔い止めを飲んだから大丈夫」と思うことで、不安を和らげる効果もあります。
乗っている間の対策
乗車時の座席選びをはじめ、乗車中にできる対策をご紹介します。
揺れの少ない場所に座る
酔いやすい方は、車なら助手席や中央付近、バスは前方、船は中央付近など、揺れの小さい場所を選んで座りましょう。窓を開けることが可能な場合は、換気されている窓側の席もおすすめです。
乗り物の進行方向を見る
頭の軸を動かさず、視線を進行方向・遠くの物体に向けるとよいです。揺れの感覚と見えている景色のずれを減らすことで、前庭小脳の混乱を抑えられる可能性があります。
これに関して、運転手は自分の動き(操作)に合わせて外の景色が動くため、感覚や視覚のずれが起こりにくく、酔いにくいと言われています。そのため、自分も運転手になったつもりで視線をまっすぐに保ち、乗り物の動きに合わせて体を傾けると酔いにくくなるのではないでしょうか。
頭をできるだけ動かさない
あごを引いて頭が揺れないようにすることで、三半規管のリンパ液や耳石器の平衡砂の動きを抑え、酔いを和らげることができます。
読書やスマホ、ゲームは控える
読書やスマホは手元の1点を見つめるため、揺れの感覚と視覚のずれが生じ、格段に酔いやすくなります。乗り物が発進してからは、進行方向に視線を向けましょう。
「酔わない」と自己暗示をかける
不安やストレスは自律神経に影響するため、ポジティブな気持ちで臨むというのも効果的です。「酔うかもしれない…」ではなく、「酔わない、大丈夫」という意識を心がけましょう。そのためには酔い止めを服用するなど、万全な体制で臨むことも大切です。
また、家族や友人と乗車する場合は会話を楽しんだり、好きな音楽を聴いたりなど、気分よく過ごせる方法を考えてみましょう。
まとめ
乗り物酔いの主な原因は、様々な刺激によって自律神経が乱れてしまうことにあります。十分な睡眠、適度な食事など、心身の健康を保つ習慣を心がけましょう。また、服装や酔い止め薬のような事前の準備も大切です。乗り物酔いに備えて快適な旅にしましょう。
私自身も酔いやすい体質ですが、「少しくらい…」という安易な気持ちでスマホをいじることをやめ、運転手に視線や動きを合わせるよう意識してからは、いくらか酔いにくくなったように思います。お悩みの方はぜひ試してみてください。