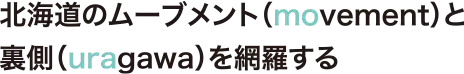「ヒグマに出会わないために」北海道登山の完全安全マニュアル
2025年4月、情報を追加しました
北海道の壮大な自然には「クマ(ヒグマ)」が生息しています。ニュースでクマの出没情報を耳にする方も多いのではないでしょうか。クマとの予期せぬ遭遇は、時に重傷や命の危険にも直結する深刻な事態を招くこともあります。登山やトレッキングを安全に楽しむためには、ヒグマに対する正しい知識と効果的な対策が不可欠です。適切な予防策を講じることで、クマに遭遇するリスクを大幅に軽減できます。
この記事では、登山前の準備から登山中の具体的な注意点、万が一ヒグマに遭遇した時の正確な対処法までノウハウを徹底解説します。北海道の自然を満喫したい方は、命を守るためにぜひ参考にしてくださいね。
北海道の山に生息するヒグマの生態と特徴
北海道にのみ生息する「ヒグマ」とは?「ツキノワグマ」との決定的な違い
日本国内では北海道にのみ生息するヒグマは本州に生息するツキノワグマ(体重60kg~130kg、体長120~150cm)と比較すると、体重80kg~200kg、体長1.5m~2.3mほどと体格が格段に大きく、力も強いのが最大の違いです。四足歩行が基本ですが、後ろ足で立ち上がると人間をはるかに上回る体格となり、その威圧感は圧倒的です。本来、人間を避ける臆病な性格ですが、突然の出会いによる恐怖心や防衛本能から攻撃的になることがあります。また、人間の残した食べ物に誘引されて人の生活圏に接近するケースも増加しています。
北海道でクマに遭遇しやすいエリア&時期
ヒグマは主に山岳地帯や森林地帯に生息していますが、特に以下のような場所では遭遇リスクが高まるため注意が必要です。
●山菜や果実が生えている場所
●川や沼、湖など水源の近く
●過去に出没情報がある場所
●人が歩かない未開の道
活動が活発になる時期としては、冬眠明けの4月頃から食料確保のために行動範囲を広げ始め、夏から秋にかけて冬眠前の栄養蓄積のために特に活発になります。6月〜10月は特に注意が必要な時期です。
【事前対策】登山前に実践すべきクマ対策の基本
クマ出没情報の確実な調べ方と情報源
北海道で登山をする際は、必ずヒグマの出没情報を事前確認することが安全確保の第一歩です。以下の情報源を複数チェックし、最新状況を把握しましょう。
●各自治体の公式ウェブサイト:「ヒグマ出没情報」のページを確認
●北海道森林管理局や環境省の情報:特に国立公園内の最新警戒情報
●登山口やビジターセンター:最新の注意喚起情報を確認
●登山アプリやSNSのコミュニティ:実際の登山者による目撃情報も貴重
●地元ガイドや山岳会の情報:経験者からの最新アドバイスを得る
直近のクマ出没情報が多い地域への登山は、安全のために延期や別ルートへの変更を検討すべきです。
【熊の目撃について】
— 北海道警察地域情報発信室 (@HP_tiiki) October 28, 2024
令和6年10月28日午後0時36分頃、札幌市南区定山渓温泉東1丁目で、熊の目撃通報がありました。
警察官等が現場付近を警戒していますが、同所付近を通行する際は十分に注意してください。
また、熊を目撃した場合には110番通報をお願いします。#ヒグマ
SNSの情報はリアルタイムで更新されているので確認しやすいですね!
「クマ鈴」だけでは不十分!効果的な音による存在アピール法
クマ鈴は最も一般的なヒグマ対策グッズとして、登山者がよく使うクマ避けアイテムで、リュックやベルトに身に付けて使います。歩くたびに鈴の音が鳴りクマを寄せつけない効果があるといわれています。アウトドアショップで購入できます。ただ、これだけに頼るのは危険です。以下の理由から複合的な音対策が必要となります。
●ヒグマが鈴の音に慣れている可能性:頻繁に人が訪れる場所では効果減
●風や川の音でかき消される:環境によっては音が届かないことも
●ヒグマの警戒心の個体差:若いクマは人間に対する警戒心が薄いことも
より効果的な音対策の組み合わせ
●定期的な声出し(「クマさんいませんか」など具体的なワード)
●手拍子や木の棒で地面を叩く音
●トレッキングポールを岩に打ち付ける金属音
●ホイッスルの定期的な使用(特に視界の悪い場所)
●小型ラジオの活用(人の声が継続的に流れる効果)
これらを組み合わせて定期的に音を出し、ヒグマにこちらの存在を適切に知らせることが重要です。
登山必携!推奨するクマ対策グッズ5選と正しい使用法
北海道の登山では、以下のヒグマ対策グッズを必ず携行しましょう、
●クマ撃退スプレー
使用期限を確認し、取り出しやすい位置に装着します
使用前に風向きを必ず確認(逆風での使用は厳禁)
有効射程距離(3〜5m)を把握しておく
●大音量ホイッスル
クマに気づかせるために有効
緊急時に120デシベル以上の音が出るものを選びましょう
首からぶら下げるなど、すぐに使える位置に保管
●防臭 / 防水性のある食料保存袋
食品の匂いを完全に遮断する密閉袋
食べ物はすべてこの袋に入れて管理しましょう
●クマ鈴
リュックの上部など音が響きやすい位置に取り付け
●LED強力ライト
夕暮れ時や早朝の視界確保と威嚇用に
500ルーメン以上の明るさを推奨
これらのグッズはアウトドアショップやオンラインショップで購入できます。使用方法を事前に確認し、いざという時に慌てずに対応できるよう準備しておきましょう。
【実践編】登山中にクマに遭遇しないための具体的行動ガイド
ヒグマを寄せ付けない!登山中の正しい「クマ避け行動」とNG行為
ヒグマは人の気配に気づかず、突然接近するとパニックを起こすことも。基本的に臆病で、人間を避ける傾向にありますが、驚くと人を襲ってしまう危険が高まります。突然の遭遇は双方にとって危険です。以下の行動を心がけましょう
推奨するクマ避け行動
●継続的な存在アピール
定期的に大きな声を出す
●グループ行動
複数のほうがクマは警戒するので3人以上での行動が理想的(単独行動は極力避ける)
●風上からの接近
ヒグマに自分の匂いを察知させる
●視界の確保
茂みや急カーブでは特に注意喚起を増やす
●休憩時の周囲確認
食事や休憩前に周囲の安全を確認する
✕ NG行動
●無言での行動
静かに歩くことでクマを驚かせるリスク大
●イヤホン使用
周囲の音(クマの気配)に気づけない
●食べ物のにおいを漂わせる
強い匂いの食べ物を開けっ放しにする
●夜間の行動
視認性が低下し遭遇リスクが高まる
●ヒグマの通り道を塞ぐ
逃げ道がなくなると攻撃的になる可能性
特に注意すべきはイヤホンやヘッドフォンの使用です。音楽を聴きながらの登山は、クマの存在に気づけないだけでなく、自分の発する音でクマに存在を知らせることもできません。「今、人間がここにいるよ」とクマに知らせることを意識して歩くのがおすすめです。黙々と歩きたくなる気持ちはわかりますが、クマ対策には適しません。
引き返すべき警告サイン!クマの痕跡と察知方法
登山中に以下のようなヒグマの痕跡を発見した場合、すぐ近くにクマがいる可能性が高いです。その場から静かに引き返し速やかに安全な場所へ移動しましょう。特に複数の痕跡が同時に見つかる場合は、ヒグマの活動が活発なエリアである可能性が高いです。
緊急性の高い痕跡
●新鮮な足跡:成獣の足跡は幅15cm以上で爪痕が明確
●新しい糞:湿り気があり、ベリー類の種や獲物の骨片を含む
●引っ掻き傷のある木:新鮮な樹皮剥ぎや爪痕(縄張り表示の証拠)
●食べられた動物の死骸:ヒグマのエサ場になっている可能性
●クマの唸り声や独特の臭い:すぐ近くにいる証拠
これらの痕跡を発見した場合の対応
●大きな音を立てずに、その場を静かに離れる
●来た道を引き返す
●他の登山者にも情報を共有する
●安全な場所(登山口など)まで戻ったら関係機関に通報する
【緊急時対応】もしクマと遭遇した場合の正確な対処法とやってはいけないNG行動
最重要!クマと遭遇した瞬間にすべき行動と絶対NGな対応
ヒグマと遭遇した場合、その後の数秒間の行動が生死を分ける可能性があります。まず絶対にやってはいけないのが「走って逃げる」ことです。逃げるものを追う習性があるため、ほぼ追いかけられてしまうでしょう。ヒグマは時速50km以上の速さで走れるため、追いかけられたら逃げ切るのは不可能です。冷静に以下の対応を取りましょう。
◯ 正しい対応
●その場で静止する:突然の動きはクマを刺激する
●落ち着いた声で話しかける:低く穏やかな声でクマに人間だと認識させる
●ゆっくりと後退する:目を合わせず、斜め45度方向にゆっくり後退
●大きく見せる:リュックは背負ったまま、決して荷物を投げるなどして注意をそらさず、腕を広げて大きく見せる
✕ 絶対にしてはいけないNG行動
●走って逃げる:追跡本能を刺激し、時速50kmで追いかけられる
●クマと目を合わせる:挑発と受け取られる危険性
●大声で叫ぶ:攻撃的な印象を与える
●クマに背を向ける:弱い獲物と認識される可能性
●食べ物を投げる:人間=食料源という関連付けを強める
あわてて逃げるとクマは追ってきます。攻撃される危険があるのでゆっくり後ろに下がりましょう。物を遠くに投げて興味をそらすのは逆効果です。人間に興味を持ったり、驚いて攻撃してきたりする可能性があります。クマを刺激しないよう、落ち着いて対応してください。
「死んだふり」は効果なし!クマへの対応策
よく聞くクマへの対応「死んだふり」は、基本的に効果がありません。特にヒグマの場合、興味を持たれると攻撃される可能性が高いため伏せるのは危険です。代わりに、ゆっくり後退しながら、クマに「敵意がない」ことを伝える行動が重要です。死んだふりは絶対しないようご注意くださいね。その理由と実際に有効な対策を解説します。
✕ 死んだふりが効かない理由
●ヒグマは死んだ動物も食料とするため興味を引く
●地面に伏せることで弱い存在と認識される
●防御力がなくなり、クマの好奇心を刺激する
◯ 科学的に有効な対策
●大きく見せる戦略:リュックを背負ったまま、両腕を広げる
●集団での対応:複数人で固まり、大きな集団に見せる
●威嚇行動への対抗策:クマが威嚇してきたら、むしろ大きな声を出す
●横方向への移動:クマの進路を妨げない方向に退避する
クマ撃退スプレーの正確な使用タイミングと効果を最大化する方法
クマ撃退スプレーは、適切に使用すれば90%以上の確率でヒグマの攻撃を阻止できる効果的な防衛手段です。以下にその正確な使用法を解説します
最適な使用タイミング
●クマが5〜10m以内に接近し、こちらに向かってくる場合
●他の回避手段が通用せず、攻撃の危険が迫っている場合
効果的な使用方法
●風向きを確認:風上または横風の状態で使用(逆風は厳禁)
●安全装置を解除:使用前に必ず安全ピンを外す
●適切な狙い:クマの顔面、特に目と鼻の周辺を狙う
●短く強く噴射:1〜2秒の噴射を2〜3回繰り返す
●噴射後の行動:クマが怯んだ隙に、ゆっくりその場を離れる
注意点
●スプレーの主成分であるカプサイシンは、クマの粘膜を強く刺激し一時的に視覚と嗅覚を奪います
●使用者も影響を受ける可能性があるため、風向きには特に注意が必要
●有効期限(通常2〜4年)を過ぎたスプレーは効果が低下するため定期的な交換を
クマ撃退スプレーは最終手段です。可能な限り事前の予防策を徹底し、遭遇自体を避けることが最も重要です。
北海道の登山でクマ対策を徹底しよう
ヒグマを山に引き寄せない!登山者が守るべき環境マナーと食料管理
自然を守りつつ、ヒグマと人間の安全な共存のためには、登山者一人ひとりの適切な行動が不可欠です。ヒグマ対策をするための必須マナーはこちらです。
食料・ゴミの管理
●完全なゴミの持ち帰り:食べ残しやティッシュも含めすべて持ち帰る
●食料の密閉保管:臭い漏れ防止袋の使用を徹底
●調理場所と寝床の分離:キャンプ時は50m以上離す
●残飯の処理:汁物などは指定された場所で適切に処理
テント場での注意点
●テント内に食料や歯磨き粉など香りのするものを持ち込まない
●食料は熊よけネットや専用コンテナを使用(木の枝に吊るすのは不適切)
●夜間のトイレ移動は複数人で行動
ヒグマを人間の食料に慣れさせないことが、将来的な事故防止にもつながります。一人ひとりの責任ある行動が重要です。ヒグマは怖がりなので、複数人のほうが警戒します。登山をするときは、ヒグマが棲んでいるテリトリーにおじゃまする気持ちで行くといいですね。
クマを見かけたらどこに通報する?正確な通報方法と記録すべき重要情報
ヒグマを目撃した場合、できるだけ速やかに通報してください。他の登山者や関係機関への情報共有は極めて重要です。以下の手順で適切に通報しましょう
通報先機関
●最寄りの警察署:110番(緊急時)または最寄り警察署の直通番号
●環境省自然保護官事務所:国立公園内の場合
●各自治体のヒグマ対策担当部署:地域によって異なる
●森林管理署:国有林内の場合
●登山口:掲示板に最新情報を記入
他の人のためにも、ヒグマを見かけたら情報を提供しましょう。まずは、自治体や警察、森林管理局に連絡をするとスムーズに対応してくれます。また、他の登山者に知らせるためにも。登山口に記録するものがあればお知らせしてください。ヒグマの数やいた場所、時間などをなるべく細かく記載すると、他の人が参考にしやすいですよ。
記録・通報すべき情報
●目撃日時と正確な場所:GPS座標があればベスト
●ヒグマの特徴:数、大きさ、毛色、子グマの有無
●行動の様子:移動方向、人間への反応
●痕跡の状況:足跡や糞、食痕などの新しさ
●あなたの対応:取った行動と結果
これらの情報は登山アプリでも共有し、他の登山者の安全確保に貢献しましょう。正確な情報が次の事故防止につながります。
【《緊急》ヒグマ出没情報】(豊平区羊ヶ丘)
— 札幌市広報部 (@Sapporo_PRD) September 14, 2022
先ほど、豊平区羊ヶ丘の札幌ドーム敷地内にヒグマがいるとの通報が寄せられました。
詳細が分かり次第、追ってお知らせしますが、大変危険ですので周辺の方は不要な外出を控えていただくなど注意願います。ヒグマを目撃したら110番通報願います。
【まとめ】クマ対策をして北海道での登山を安全に楽しもう
北海道の山々は、その壮大な自然景観と豊かな生態系で多くの登山者を魅了しています。その反面、北海道はヒグマが多く生息し、遭遇するリスクも高いためクマ対策は必須。適切な対策を講じることが不可欠です。クマの生態や対策法を知って、事前準備を万全にしてから登山をすると安心です。
私たち人間がヒグマのテリトリーに入るという認識を持ち、敬意を払いながら適切な対策を取ることで、双方にとって安全な共存が可能となります。ルールを守り、北海道の美しい自然を安心して楽しんでくださいね。
●ヒグマの生態と特性を理解する
●事前の情報収集と準備を徹底する
●適切なクマ対策グッズを携行する
●登山中の正しい行動パターンを身につける
●万が一の遭遇時に冷静に対応できるよう心構えをする
●環境に配慮した責任ある行動を取る